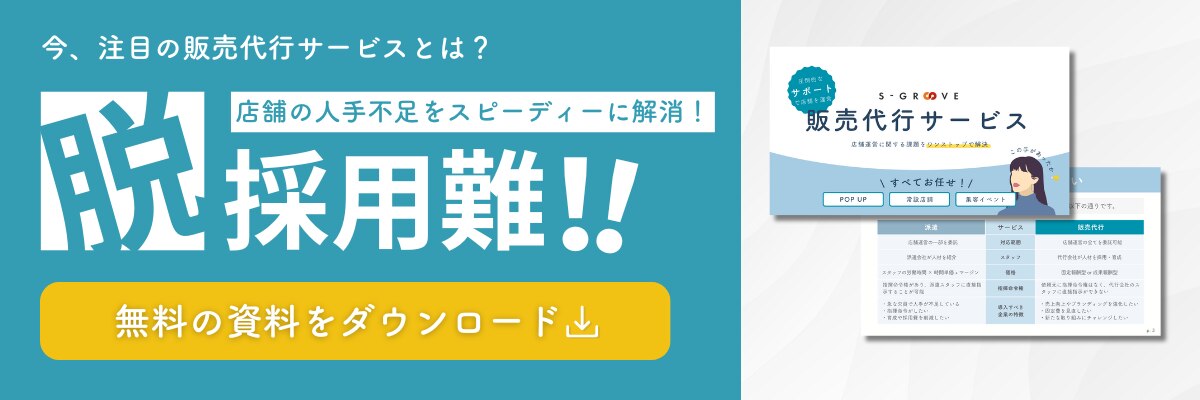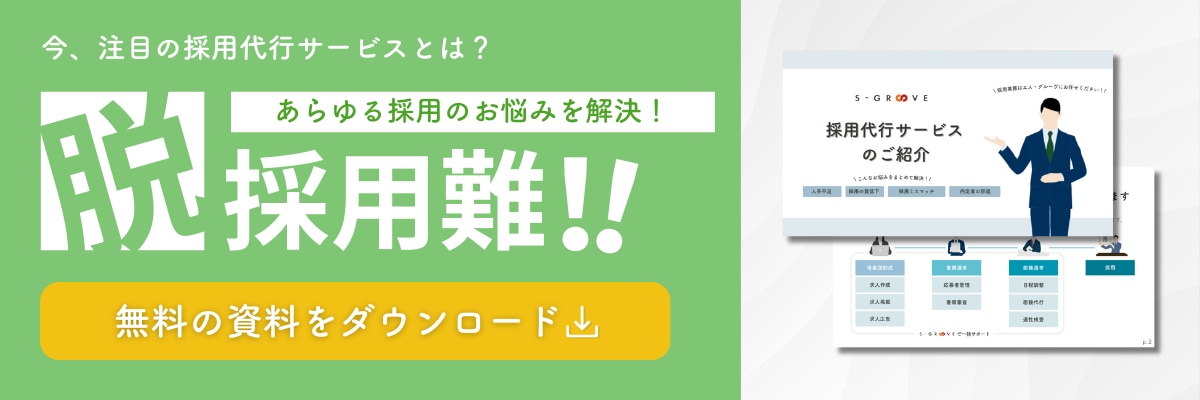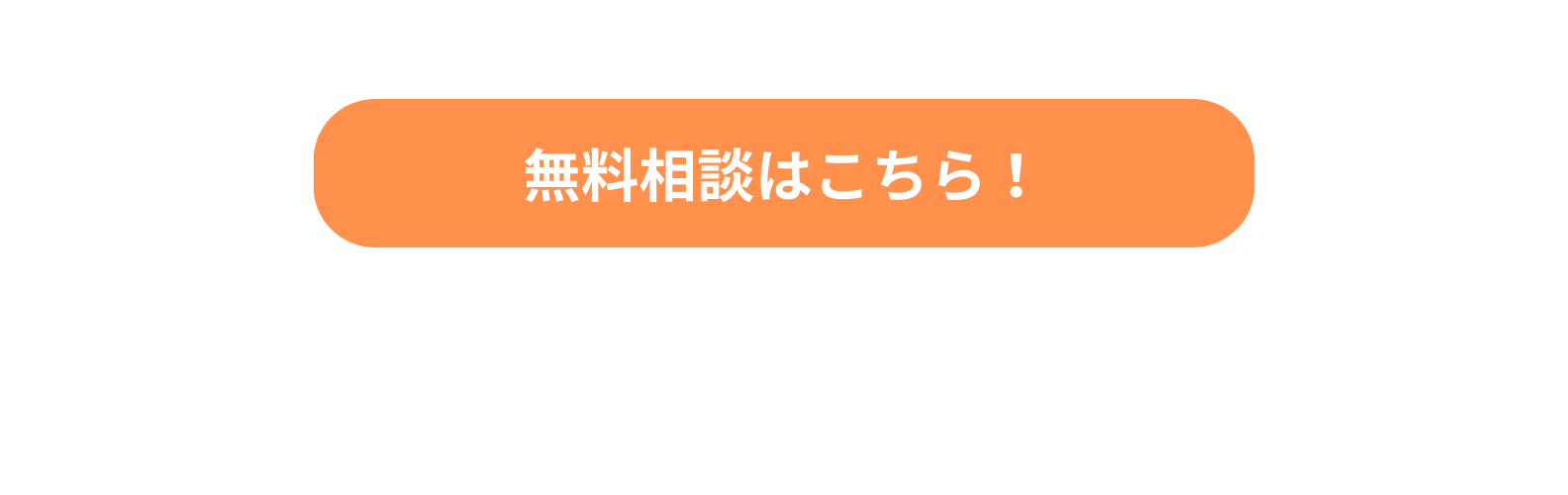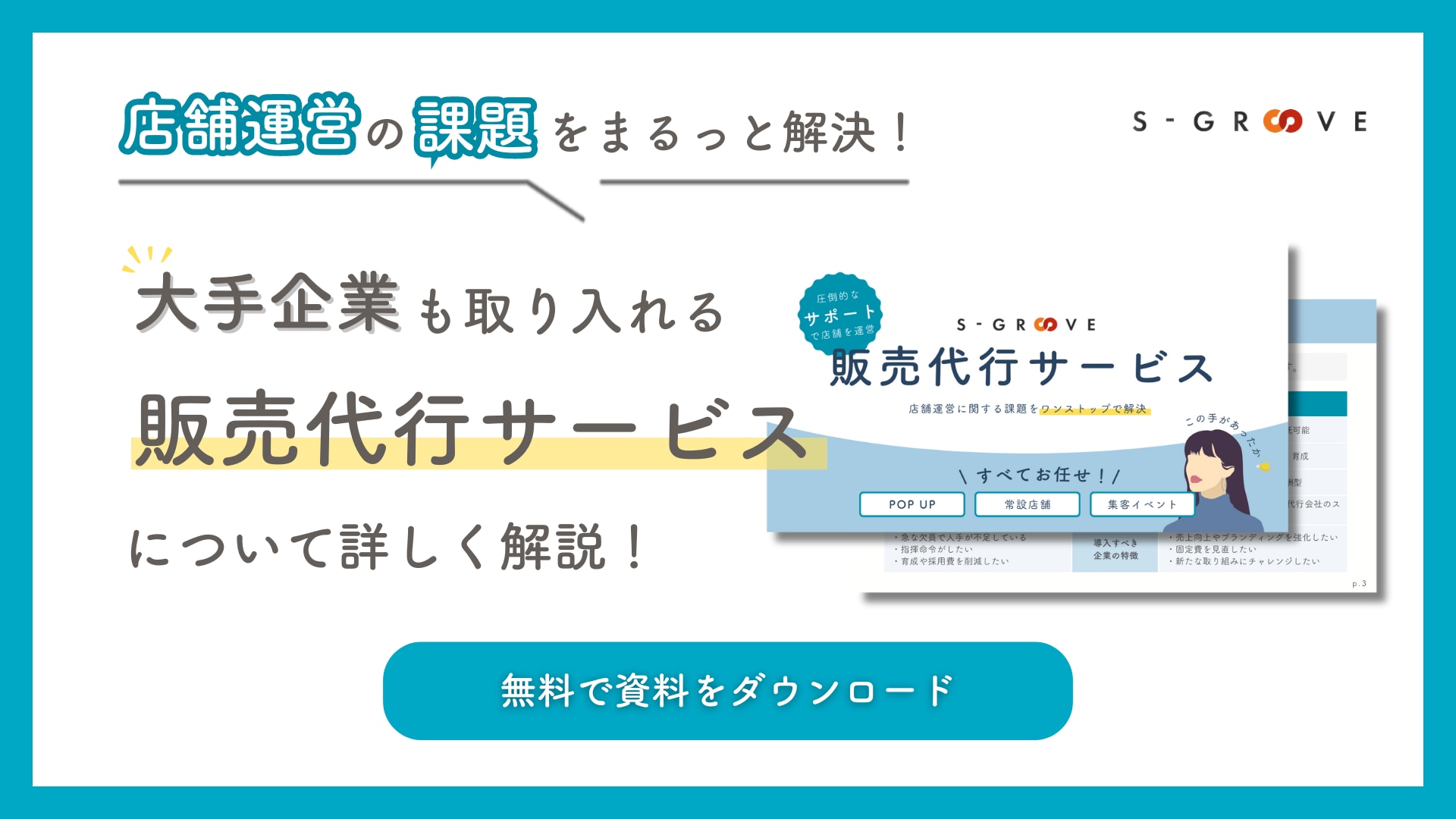アパレル業界必見!自社ブランドにマッチした人材要件の作成方法とは?
アパレル業界は、常に変化するファッショントレンドや消費者のニーズの多様化を背景に、動きの激しい市場です。
このような環境下で、企業やブランドが成功を収めるためには、優秀な販売員の確保が非常に重要です。
販売員の人材管理は、顧客満足度や売上の向上に大きく寄与し、貴社の成長を支える基盤となります。
本記事では、自社にマッチした人材要件の作り方について詳しく解説します。
▼採用難を脱却する「販売代行サービス」とは?
目次[非表示]
- 1.そもそも採用要件とは?
- 2.アパレル業界で採用要件の定義が求められる理由
- 2.1.採用市場の変化
- 2.2.転職に関する価値観の変化
- 2.3.入社後の離職防止
- 2.4.働き方の多様化
- 3.採用要件を定めるメリット
- 3.1.応募者を適切に評価できる
- 3.2.採用ミスマッチを軽減できる
- 3.3.円滑な採用活動ができる
- 4.採用要件の作り方
- 5.人材要件を定める際のポイント
- 5.1.厳しくしすぎない
- 5.2.定期的に条件を見直す
- 6.まとめ
そもそも採用要件とは?
採用要件とは、自社が求める人材像を具体的に定義したもので、以下のような項目を基準に決定します。
● 労働条件 ● 必要な経験やスキル ● 求める価値観 ● 人柄 ● 行動特性 |
採用要件が曖昧だと、企業と採用者の間でミスマッチが生じ、企業ないしはブランドが目指す姿の実現が困難になります。
▼関連記事|採用基準の設定方法とは?
アパレル業界で採用要件の定義が求められる理由
各企業はなぜ採用要件を定義づける必要があるのでしょうか。
その理由として、以下のような日本社会の変化、アパレル業界の現状が関係しています。
● 採用市場の変化 ● 入社後の離職防止
|
採用市場の変化
採用要件を強化すべき理由として、日本社会の課題でもある少子高齢化による採用市場の変化が挙げられます。
内閣府の「令和4年版 少子化社会対策白書」によると、総人口減少に伴い15~64歳の労働人口が年々減少していることが分かります。
2053年には、総人口が1億人を割ると予測されており、ますます少子高齢化社会が加速すると予測されています。
このような社会情勢から、企業は少ない労働人口から優秀な人材を獲得するために「待ちの採用」ではなく「攻めの採用」に切り替え、自社で活躍できる人材を積極的に確保していく必要があるのです。
転職に関する価値観の変化
転職市場は活発化しており、転職に対するハードルが下がっています。
これは特にミレニアル世代やZ世代に顕著で、キャリアアップの手段として積極的に捉える動きが強まっています。
さらに、働き方の多様化により自己成長や社会貢献、ワークライフバランスを重視する傾向があります。
転職市場が活発化する現在、採用要件をしっかりと定め、定着率の向上を図る必要があるのです。
入社後の離職防止
厚生労働省の調査によると、アパレル販売員を含む小売業界の離職率は41.9%と、離職率の高い上位5産業にランクインしている状況です。
小売業界のなかでは、アルバイトやパートタイムの従業員の比率が少ない傾向にあり、正社員にかかる負担が大きいとされています。
アパレル業界は華やかな印象がありますが、入社後に「思っていたのと違う」と感じて離職してしまうケースは少なくありません。
採用要件をしっかりと定め、選考過程での相互理解を深めることによって、ミスマッチを軽減し、短期離職による損失を最小限に抑えることが可能です。
出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者) 」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)
働き方の多様化
デジタル化の進展により、販売の現場や業務内容は目まぐるしく変化しています。
オンラインチャネルの成長により、店舗で働く販売員には従来の販売技術に加え、SNS運用をはじめとするデジタルスキルやデータ分析能力が求められるようになりました。
企業は顧客の新しいニーズに対応するため、柔軟で包括的な採用要件を策定する必要があります。
▼現在のアパレル販売員に求められるスキルとは?
▼【無料ダウンロード】採用難を乗り切る採用支援サービスとは?
採用要件を定めるメリット
応募者を適切に評価できる
明確な採用要件は、選考過程において応募者を公平かつ適切に評価するための基準を提供します。
これにより、採用担当者は応募者の能力や適性を客観的に判断できるため、より良い人材選定が可能になります。
また、選考基準が明確であれば、面接や評価において一貫性が保たれ、適材適所の採用が実現します。
採用ミスマッチを軽減できる
適切な採用要件に基づく選考は、企業と採用者間のミスマッチを減少させる大きな効果を持ちます。
具体的な職務内容や企業文化を採用前に共有することで、入社後の不一致を防ぐことができます。
ミスマッチの軽減により、長期的な人材維持が可能になり、採用にかかるコストや時間の削減にもつながります。
円滑な採用活動ができる
採用要件が明確であると、採用プロセス全体がスムーズに進行します。
求人票作成から面接、最終選考に至るまで、誰もが同じ基準で行動できるため、コミュニケーションミスや誤解が減少します。
これにより、採用活動の効率性が向上し、結果として迅速で質の高い採用が実現できるのです。
採用要件の作り方
採用要件の作り方は、主に「演繹的アプローチ」と「帰納的アプローチ」のふたつです。
それぞれの特徴と進め方を以下で解説します。
演繹的アプローチ
演繹的アプローチは、自社の経営方針や事業内容を分析して人材要件を定義する方法です。
大きく4つのステップに分けて進めます。
①企業理念や方針の明確化 企業の目指す方向性を確認し、採用目的を明確にします。 ②関係部署へのヒアリング 各部署から必要なスキルや能力をヒアリングし、具体的な人物像をまとめます。 ③必要用件の整理 ヒアリングした要件をリストアップして、項目ごとに整理します。 具体的な項目には、「勤務地・スキル・経験・人柄」などがあります。 ④要件の優先順位を精査 MUST(必須)、WANT(希望)、NEGATIVE(評価しない)などの優先順位をつけます。 |
▼【無料!スキル一覧シート付】販売員に求められるスキルセット
帰納的アプローチ
帰納的アプローチは、自社で活躍している社員を分析し、その特性を基に人材要件を設定します。具体的なステップは以下の通りです。
①優秀な人材のリストアップ 社内で成果を上げている社員をリストアップします。 ②キャリアのヒアリング リストアップした社員に対してキャリアを洗い出し、具体的な経歴や実績を聞き出します。 ③要素の整理と分析 ヒアリングで得た情報を分析し、活躍している人材に共通する要素を見つけ出します。 ④ペルソナの設定 共通要素を基に、具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。 ※ペルソナの設定方法はこちらをご参照ください |
▼関連記事|ペルソナの設定方法を徹底解説
人材要件を定める際のポイント
厳しくしすぎない
人材要件を設定するときに求める条件を厳しくしすぎると、該当する人材が極端に少なくなり、「採用できる人材が誰もいない…」という状況に陥ってしまいます。
特にMUST(必須条件)を増やしすぎると、本来なら採用に値する人材に不合格判定を出して、採用の機会を取り逃がしてしまう可能性があります。
非現実的なほど厳しい条件を定めるのは、やめておきましょう。
定期的に条件を見直す
人材要件は、一度設定して終わりというものではありません。
設定した要件をもとに採用選考をおこない、採用した人材の動向をチェックして、「定めた人材要件は本当に適正だったか」を定期的に見直す必要があります。
検証を行なった結果、採用した人材が定着・活躍していない場合は、条件を見直して改善しましょう。
最初に定めた人材要件が必ずしも適正でない場合でも 、PDCAサイクルを回して繰り返し効果検証・改善を行なっていけば、次第に定着率の高い優秀な人材を確保できるようになります。
まとめ
アパレル企業が激しい市場競争の中で持続可能な成長を遂げるためには、正確な採用要件の設定と採用プロセスの最適化が必須です。
人材確保でお悩みの企業は、本記事を参考に採用要件を設定してみてください。
弊社は、貴社が直面する採用と定着の課題を解決するために、販売代行サービスや派遣紹介サービスを提供するファッション・ビューティー業界に特化した人材会社です。
理想的な人材を確保し、貴社のブランド成長に貢献いたします。
\ 相談だけでもOK /