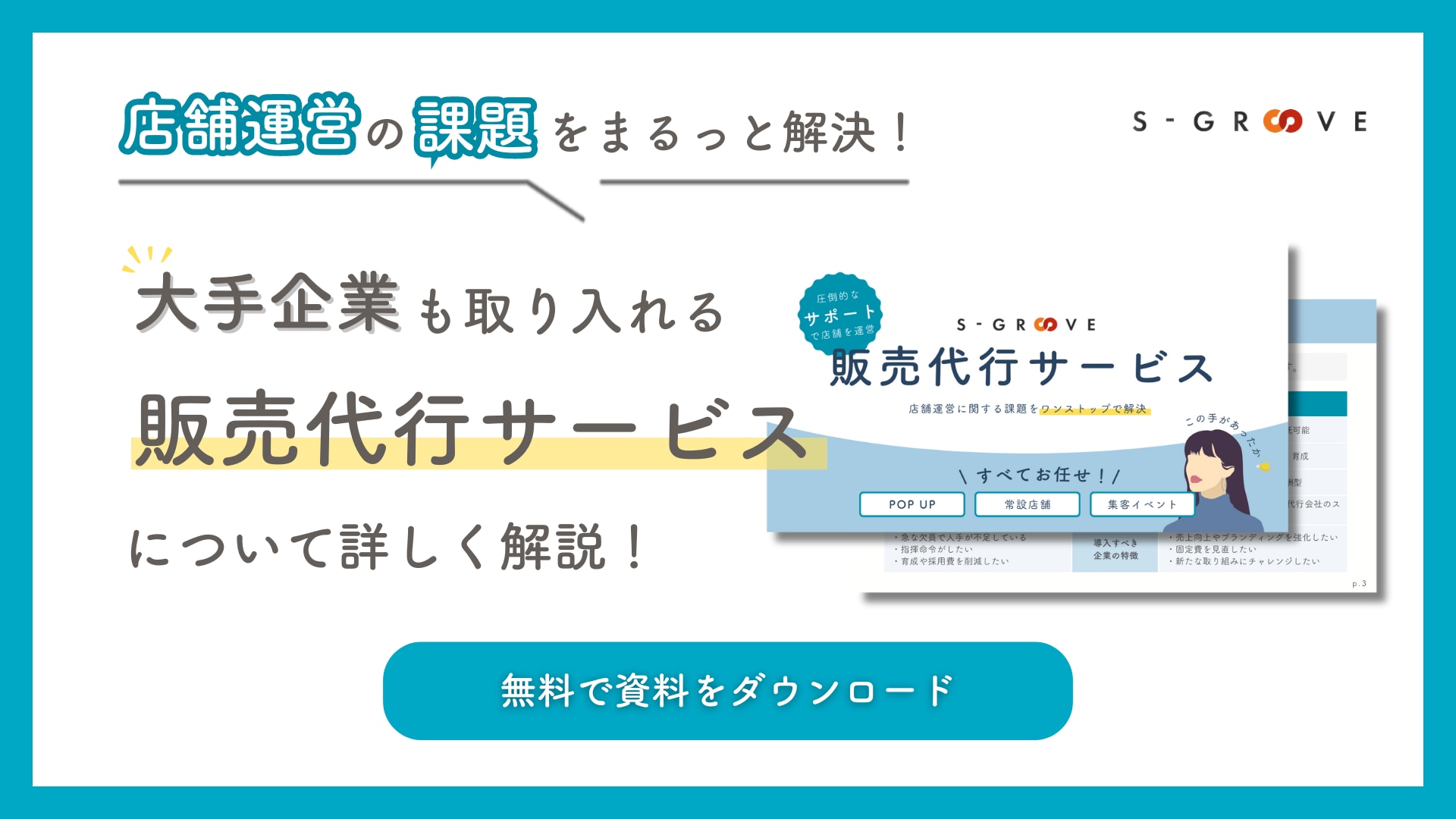アパレル企業必見|小紅書(RED)運用代行で中国市場進出を成功させる方法
中国市場で自社ブランドを広めたいアパレルメーカーにとって、小紅書(RED)は欠かせないマーケティングチャネルです。
中国版Instagramとも呼ばれるREDは、月間3億人以上のユーザーが利用するSNSで、ファッションやライフスタイル情報の収集、商品レビュー、EC利用に活用されています。
しかし、言語・文化・トレンド・アルゴリズムの壁により、RED運用は想像以上に難しいのが現実です。
本記事では、アパレルメーカーがRED運用でつまずくポイント、日本企業の成功事例、そして運用代行サービスを活用するメリットを解説します。
▼スタッフコンテンツを最大化させるスタッフコンテンツ支援サービスとは?
目次[非表示]
中国市場で急成長中の「小紅書(RED)」とは?
小紅書(RED)は中国版Instagramとも呼ばれ、月間3億人以上のユーザーを抱える人気SNSです。特に20〜30代の女性を中心に、ファッションやライフスタイル情報の収集、商品レビュー、EC利用に幅広く活用されています。
中国では「グレート・ファイアウォール(中国政府がインターネットに設定している大規模な検閲・情報統制システム)」によりInstagramが利用できないため、国内SNSである小紅書(RED)が自然と情報収集・購買プラットフォームとして定着しました。
日本ブランドや日本製品は中国ユーザーに人気が高く、最近では小紅書(RED)上での日本関連検索数も増加傾向にあります。そのため、インバウンドや中国市場拡大を狙う企業にとって、小紅書(RED)は重要なマーケティングチャネルとなっています。
小紅書(RED)の運用はなぜ難しい?つまずく3つの壁
中国語・文化理解の壁
小紅書(RED)で商品を効果的に訴求するには、中国語で自然に表現し、現地ユーザーが共感するトーンを使うことが必須です。
単なる翻訳では広告臭が強くなり、信頼や共感を得られません。
また、アパレル商材を訴求するのであれば、「着用感」や「コーディネートの工夫」など具体的な体験を交えた投稿が有効です。
しかし、中国語に精通した社内人材の採用は難しく、多くの企業が外注に頼っているのが現状です。
トレンドキャッチとビジュアル制作の壁
小紅書(RED)ではトレンドの変化が早く、投稿の企画・ビジュアルの質が成果に直結します。
ただ美しい写真を載せるだけでは評価されず、フォロワーや新規ユーザーに届きません。
効果的な投稿には、最新トレンドを取り入れたコーデ、生活シーンを意識したビジュアル、リアルな体験談が必要です。
片手間で運用するには業務量が多く、専任チームを制作する必要があります。
アルゴリズム変化への対応
小紅書(RED)はアルゴリズムが頻繁に更新され、投稿の露出は「保存・シェア・コメント・再生率」など複数の指標で評価されます。
そのため、ハッシュタグ、投稿タイミング、動画構成、キャプションを常に最適化する必要があります。
社内だけでは追いつかない場合が多く、運用代行会社や現地専門チームの支援が有効です。
小紅書(RED)運用は代行で効率化!
先述の通り、小紅書(RED)の運用は、SNS運用スキルに加え語学力や現地理解が必要になります。
スピード感を持って効果最大化を図るためには、外注で効率的に運用することをおすすめします。代行を利用するメリットは以下の通りです。
現地に合わせた戦略設計ができる
代行会社はREDを効果的に運用するための中国語・文化・トレンドを熟知しています。
ブランドの世界観を中国の消費者にどう伝えるか、どんな切り口・フォーマットが刺さるかを最適化できます。
そのため、ブランド側が「まず何を投稿すれば良いか」「どのKOLを使えば良いか」という検討を一から行う負担を軽減できます。
インフルエンサーとのマッチングがスムーズ
REDではKOL(Key Opinion Leaderの略で、特定の分野で高い専門知識や経験を持ち、消費者の購買意思決定に強い影響力を持つ人物)だけでなく、フォロワー数は多くないがリアルな影響力を持つKOC(Key Opinion Consumerの略で、一般消費者目線で口コミを発信する存在)の活用が効果的とされています。
代行会社はこれらのインフルエンサーと日頃からパートナー関係を持っており、アパレルブランドの目的・予算・世界観にあったキャスティングが可能です。また、契約・投稿管理・結果分析まで一括管理できるためブランド側の手間を大幅に削減できます。
投稿制作・運用・分析・改善までをワンストップで支援
投稿のクリエイティブ制作、投稿スケジューリング、コメント・DM対応、KOL投稿後の効果分析、保存・シェア数を高める施策までプロの運用体制がと整っています。
これにより、ブランド側では「何から手を付けていいか分からない」「運用を始めたが伸び悩んでいる」という状況を回避し、より効率的に中国市場向け発信を加速できます。
日本企業のRED活用事例
UNIQLO(ユニクロ)
日本企業の中で、中国市場における小紅書(RED)活用の成功例として代表的なのがUNIQLO(ユニクロ)です。
ユニクロは小紅書(RED)上で、レビューコンテストなどユーザー投稿を活発化させる参加型キャンペーンを実施。ユーザーによる商品レビューやコーディネート投稿を促すことで、ブランドの存在感を大きくしました。
この事例は、小紅書(RED)運用においてユーザー参加型コンテンツやレビュー投稿の活用が効果的であることを示しています。
資生堂
資生堂は、中国市場での認知度向上と販路拡大に向け、小紅書(RED)を含む主要な中国SNSの口コミデータを分析し、その結果をもとに、インフルエンサー選定や動画企画に活用しました。
インフルエンサーに依頼して制作したプロモーション動画は、多くのアクセスを獲得し、商品認知の向上につながりました。
入念な事前リサーチに基づく施策により、ターゲット層に最適化した動画の拡散が実現し、大規模な集客に成功しています。
RED運用で中国市場への第一歩を
中国市場は巨大で成長性も高く、日本ブランドにとっては大きなビジネスチャンスがあります。
しかし、言語・文化・トレンド・アルゴリズムなど独自の特性がある小紅書(RED)の運用は決して簡単ではありません。
小紅書(RED)運用代行を活用することで、ブランド側は戦略設計・投稿制作・インフルエンサー起用・分析・改善までワンストップで支援を受けられ、効率的に中国ユーザーへのアプローチを実現できます。
今こそ、小紅書(RED)運用を通じて中国市場への第一歩を踏み出しましょう。
▼無料で資料をダウンロード